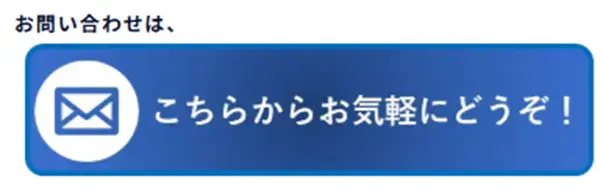ベトナム人事・労務管理の基礎知識!労働契約や就業規則、社会保険について

ベトナムの人事・労務管理では、日本と同様に、労働契約や就業規則、社会保険が存在します。
制度の内容や運用方法などで日本と異なる点も多いため、現地の法律や慣習を正しく把握せずに進めてしまうとトラブルにつながる恐れがあり、注意が必要です。
この記事では、ベトナムの人事・労務管理について、労働契約や就業規則、社会保険の基本的なポイント、基礎知識を解説します。
ベトナム労働法について

ベトナムの現行労働法は2019年に改正され、2021年1月1日から施行されています(以下「労働法」)。
労働者の権利保護を目的に、労働時間や賃金、休暇、労働契約の締結・終了、労働安全衛生など幅広い内容を定めており、なかには日本の労働基準法と類似する点も見られます。
ベトナムの労働契約の種類

ベトナムでは、労働契約の形態が法律で厳格に分類されています。
①期限の定めがない労働契約 | 無期雇用契約 |
②期限の定めがある労働契約 | 有期雇用契約 |
日本では、②のような有期契約の更新が繰り返し行われることがありますが、ベトナムでは短期契約の連続利用は制限されています。 また、旧法では12ヶ月未満の短期労働契約が認められていましたが、2019年の法改正により廃止となりました。
試用期間
ベトナムの試用期間は条件ごとに上限が定められています。
管理職 | 180日以内 |
高度専門職(大学・短大卒以上) | 60日以内 |
技術工員・専門スタッフ | 30日以内 |
その他一般業務 | 6営業日以内 |
試用期間中の給与は正規雇用時の85%以上と規定されています。
試用期間中は、労働者および使用者双方が予告なしに契約を解除できますが、1ヶ月未満の契約に試用期間を設けることは禁止されています。
労働時間・休憩時間
ベトナムの労働時間は1日8時間、週48時間が基本です。
しかし、労働者に有害な作業や危険業務が含まれる場合は、短縮勤務の規定があります。
時間外労働は月40時間、年間200時間が上限で、特定の業種、職種、業務の場合には事前通知を行えば300時間まで延長可能です。
休憩時間については、連続労働が6時間を超える場合、少なくとも30分の休憩が必要となります。
有給休暇は勤務1年につき12日が基本で、勤続年数が長くなると加算される仕組みです。
職場における秩序と行動規範
ベトナムの就業規則には、職場での行動規範を明記する必要があります。
服装規程、業務上の倫理、禁止行為(無断欠勤、飲酒、社内規程違反など)を具体的に定めることで、労働規律処分の根拠が担保され、トラブルを防ぐ仕組みとして機能するでしょう。
労働安全衛生管理
ベトナムの労務管理では、職場の安全確保も重要な要素です。
企業は労働災害防止のために定期的な安全教育を実施し、保護具を提供する義務を負います。
労働安全衛生法では、労働者の健康診断や有害物質管理についても定められており、違反した場合は企業責任が追及されます。※1
職場におけるセクシャルハラスメント
2019年の労働法改正後に、セクシャルハラスメント防止規定が明文化されました。
就業規則には「セクシャルハラスメントの定義」と「労働規律処分の内容」を記載することが義務化されています。
被害者は労働契約解除を請求でき、企業は予防教育の実施や相談窓口の設置を行うことが求められます。
労働契約と異なる業務に一時的に労働者を異動させる場合の規定
労働法第29条第1項に基づき、使用者は経営上の必要性から労働者を契約と異なる業務に一時的に配置できます。
ただし、異動させる期間は累計60日までが原則です。
日本と異なり、業務の変更に強い制限があるため注意が必要です。
労働者の労働規律処分
ベトナムでは、労働規律処分の手続きが法律で厳格に定められています。
処分形式は以下の通りです。
・譴責
・6ヶ月を超えない昇給期日の延期
・職位降格
・解雇
また、労働規律処分は労働組合の立ち会いの下で行われなければ無効となるなど、手続きの適正性が非常に重要です。
懲戒処分権限を有する者
労働法では、労働規律処分を行えるのは労働契約を締結する権限を持つ者、またはその権限を正式に委任された者に限られます。※1
通常は企業の法定代表者や代表取締役が該当しますが、委任状により人事部長や現地責任者に権限を移譲することも可能です。
無権限者が懲戒処分を行った場合、処分は無効とされ、労働争議の原因となる恐れがあります。
そのため、労働規律処分を実施する際は、誰が権限を有しているかを明確にし、社内規程や委任文書で裏付けを整えておくことが必要です。
物的責任・損害賠償
従業員が企業の資産を故意または過失により損壊した場合、損害額に応じて賠償責任を負います。就業規則に規定することで、一定の範囲で給与から賠償金を控除することが可能です。
ベトナム就業規則作成の流れ

続いては、実際の就業規則作成から、運用までの流れを解説します。
従業員からの意見聴取
ベトナムで就業規則を策定する際には、社内労働組合または従業員代表から意見を聴取するプロセスが必要です。 単なる形式的な手続きではなく、従業員側の意見を反映させることでトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
例えば、労働時間のシフト制運用や労働規律処分の基準など、従業員に直接影響する内容については十分な説明と合意形成が求められます。
意見を聞かずに一方的に規則を定めた場合、労働規律処分や労働契約解除の効力が否定されるリスクがあるため注意が必要です。
ベトナム内務局への登録
ベトナム企業は就業規則の公布が義務付けられており、従業員を10名以上雇用する場合は、書面を作成した上で企業所在地の管轄内務局への登録が義務付けられています。※1 オンラインでの申請が可能な地域も増えています。
提出後、規則の内容が労働法に違反していないかが審査されます。不備がある場合は修正指示が出され、そのままでは効力を持ちません。
そのため、外資系企業は弁護士や労務コンサルタントのサポートを受け、法令適合性を確認したうえで提出することが一般的です。
規則の周知および掲示
労働局に受理された後は、従業員に対して規則を周知する義務があり、公表や掲示が行われていないとみなされた場合には会社に罰金が科される場合があります。
印刷して配布するほか、社内イントラネットに掲載したり、職場の見やすい場所に掲示すると良いでしょう。
周知義務を怠ると、労働規律処分が無効とみなされる場合があります。
ベトナム社会保険の概要と改正について
 ベトナムで従業員を雇用する場合は、社会保険制度についても理解する必要があります。
ベトナムで従業員を雇用する場合は、社会保険制度についても理解する必要があります。
ベトナムの社会保険、健康保険、失業保険は、いずれも雇用主(使用者)と労働者の双方が拠出する仕組みです。
企業は従業員を雇用した時点から、社会保険の加入手続きを行う義務があります。
加入漏れや未払いは厳しい行政処分や罰金の対象となりえるため注意しましょう。
社会保険
社会保険(Social Insurance)は、年金や傷病、出産、労災・職業病に関連する給付を目的としています。
企業は給与の一定割合を拠出し、従業員も負担を分担します。
具体的には、雇用主(使用者)が給与の17.5%、労働者が8%を拠出することが法令で定められています(2025年時点)。
対象は労働契約が1ヶ月以上の従業員で、ベトナム人だけでなく、条件を満たす外国人労働者も加入が義務化されています。
健康保険
健康保険(Health Insurance)は、医療費負担の軽減を目的とする制度です。
雇用主(使用者)は給与の3%、従業員は1.5%を拠出し、合計4.5%が健康保険基金に充当されます。
これにより従業員は指定病院での診察や入院費用の80%をカバーでき、社会的セーフティネットとして機能しています。
失業保険
失業保険(Unemployment Insurance)は、従業員が失業した際に一定期間の生活を支える制度です。雇用主(使用者)と労働者がそれぞれ1%ずつ拠出し、さらに政府が1%を負担する仕組みになっています。
失業給付を受けるには、3か月以上の雇用契約を有するベトナム人で、過去24ヶ月のうち12ヶ月以上保険料を納付している必要があり、給付額は直近6ヶ月の平均給与の60%が目安です。
なお、外国人は失業保険に加入することはできません。
ベトナム人事・労務管理は「エスコンサルティング」にご相談ください

労働契約の種類や就業規則の作成義務、社会保険や健康保険、失業保険の加入手続きなど、企業が守るべきルールは多岐にわたります。
加えて、頻繁な法改正や労働局への登録義務、労働規律処分の正しい運用など、現地特有の注意点も少なくありません。
エスコンサルティングは、ベトナムでの豊富な実務経験を活かし、最新の法令に基づいた労務管理をサポートします。
現地法人の設立や労働契約の整備、社会保険対応まで幅広く相談できるため、外資系企業や新規進出企業にとって強い味方となります。
労務リスクを回避し、安心して事業を拡大するために、ぜひ専門家へのご相談をご検討ください。
※1 Vietnam Social Security「Official Number: No. 45/2019/QH14」