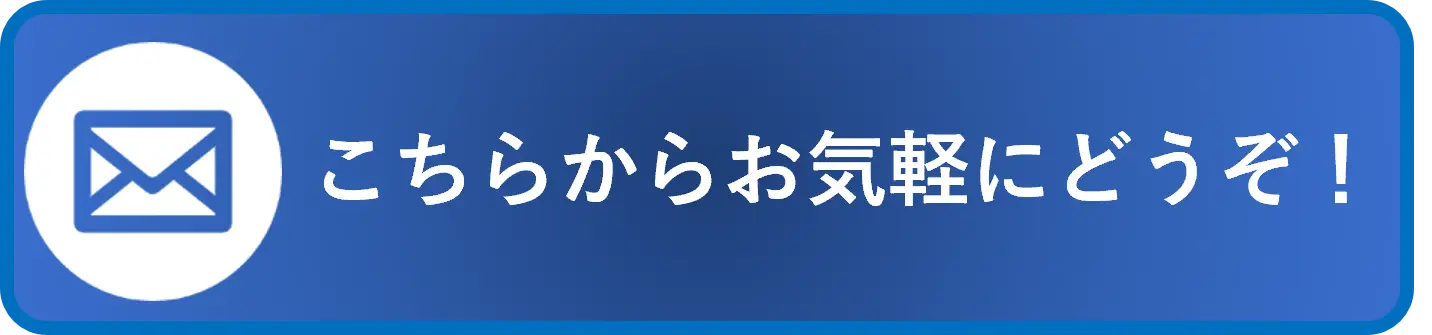フィリピンM&Aの手続と留意点【2025年最新版】
ES NETWORKS PHILIPPINES INC. 高田 真
はじめに
コロナ禍以降、フィリピンにおけるM&Aは一時的に低調となっていましたが、2024年には取引件数・金額ともに大幅に増加し、再び活発化しています。フィリピン経済は2024年、2025年と堅調に成長を続けており、今後も中長期的な成長が見込まれています。加えて、人口約1億1,000万人のフィリピンは東南アジアでも有望な消費市場であり、外務省の2024年の海外進出日系企業拠点数調査によれば、日系企業の進出も1,600社を超えると言われています。
こうした背景から、ベトナムと並び「フィリピンM&A」は、日本企業が東南アジア戦略を検討する際の重要な選択肢となっています。すでに現地で実績のある企業を買収することで、フィリピン市場へのスピーディーな参入を実現できる一方、法制度・外資規制・ガバナンスなど、現地特有のリスクや留意点も存在します。
本記事ではフィリピンにおけるM&Aの一般的な手続きと留意点について解説します。
1. フィリピンにおけるM&A手続の一般的な流れ
フィリピン企業を対象とするM&Aの基本的なプロセスは、日本国内のM&Aと大きくは変わりません。一般的に、次のようなステップで進みます。
1-1. 基本的なプロセス
- 買収戦略の立案
- ターゲット企業の選定・アプローチ
- 秘密保持契約(NDA)の締結・情報開示
- 条件表・基本合意書(LOI / MOU)の締結
- デューデリジェンスの実施(法務・財務・税務・ビジネスDDなど)
- 株式売買契約(Share Purchase Agreement)の交渉・締結
- 各種承認・届出の取得(クロージング条件)
- 株式譲渡(クロージング)と対価の支払い
1-2. フィリピン特有の承認・届出
上記のうち、日本と比べて特に注意すべき点が「各種承認・届出」です。
- 外資比率が40%超となる場合の登録
買収により現地企業の外資比率が40%を超える場合、外国投資法(Foreign Investments Act)に基づく登録を証券取引委員会(SEC)に行う必要があります。 - 外資規制(ネガティブリスト)の確認(2-1にて後述)
対象会社の事業内容がネガティブリストに該当するかどうかを確認することが重要です。場合によっては、外資出資比率の調整や、フィリピン人パートナーとのジョイントベンチャー設立など、ストラクチャーの工夫が求められます。 - フィリピン競争委員会(Philippine Competition Commission:PCC)による審査
一定の資産・売上規模を超えるM&A取引を実施する場合、PCCへの事前届出・審査が義務付けられ、承認が出るまでクロージングを行うことができません。 - 業種規制に基づく主管官庁の許認可
金融、通信、エネルギー、インフラなど、特定の規制業種では主管官庁の許認可が必要になる場合があります。 - 税務当局による納税証明取得と名義書換
株式譲渡により発生するキャピタルゲイン税(Capital Gains Tax)や印紙税(Documentary Stamp Tax)の申告・納付を行い、税務当局からの確認を得てはじめて株主名簿の名義書き換えが完了します。
このように、基本フローは日本と共通しつつも、外資規制・競争法・業種規制・税務手続など、クロスボーダー特有の追加ステップが存在する点が、フィリピンM&Aの特徴です。
2. フィリピンM&Aにおける主な留意点
ここからは、フィリピンの企業を買収する際に特に押さえておきたい7つのポイントを解説します。
2-1. 外資規制(ネガティブリスト)のチェック
フィリピンでは、憲法および外国投資法(FIA)等に基づき、事業分野ごとに外国資本の持株比率制限が設けられています。いわゆる「ネガティブリスト(Foreign Investments Negative List (FINL)」に該当する分野は、外資が参入できる比率が法律で制限されます。
例えば、
・ 土地所有:外資40%まで
・ 広告業:外資30%まで
・ マスメディア(新聞・テレビ等):外資0%(参入不可)
そのため、日本企業がフィリピンのローカル企業を100%買収したい場合でも、対象事業が規制業種に該当すれば、法律上、完全子会社化は不可能となります。
このリスクを避けるためには、対象会社の事業がどのカテゴリーに属するかを事前に精査の上、外資出資比率の制限やフィリピンパートナーとの合弁スキームを活用するなど、ストラクチャーの検討を行うことが必要となります。
2021年に成立した小売貿易自由化法(Retail Trade Liberalization Act)の改正に伴う小売業の最低資本金要件引き下げや店舗投資要件の緩和、2022年に成立した公共サービス法改正(Public Service Act)による通信・航空・港湾などの公共サービス分野における外資100%で参入可能な範囲の拡大、同年には再エネ発電への100%外資参入が可能となるなど、外資にとって追い風となる制度改正も進んでいます。一方で、土地所有、マスメディア分野等には依然として外国資本制限が残存しており、投資設計時には留意が必要です。
2-2. 財務情報の信頼性(二重帳簿・税務リスク)
フィリピンのローカル企業(特に中小企業)では、「実態と税務申告用の数字が必ずしも一致していない」ケースが珍しくありません。
- 売上・利益の一部を申告から外して税負担を軽減している
- 内部管理用の「実態ベース帳簿」と、税務申告用の「公式帳簿」が乖離している
といった状況が見られます。
過去のフィリピン国税庁(Bureau of Internal Revenue:BIR)への税務申告に未払や申告漏れがある場合、買収後に追徴課税や利息、多額のペナルティが発生し得ます。
そのため、以下の観点で財務・税務デューデリジェンスを徹底することが重要です。
- 提示された財務諸表や税務申告書を鵜呑みにしない
- 実際の売上、粗利、在庫水準、債権回収状況等を多角的に検証する
- 税務コンプライアンス状況をチェックし、過去の税務調査や未払税金、潜在的な追徴リスクを洗い出す
許認可の未取得や申告漏れなどのレギュレーション違反が見つかれば、買収後に是正するためのコストと時間を見込む必要があります。実務上は、クロージング前に売り手側に是正を求めたり、買収価格の調整によりリスクをヘッジすることが一般的です。
2-3. 贈賄・汚職などコンプライアンスリスク
フィリピンでは汚職防止の取り締まりが強化されているものの、賄賂や汚職リスクは依然として無視できません。特に公共事業や許認可を行うビジネスでは、関係官庁との接触時の現金支給等の慣習が指摘されています。税関・税務当局に対する賄賂、許認可取得を円滑に進めるためのファシリテーションペイメント、取引先に対する過大なリベート・キックバックなど、注意が必要です。
買収対象企業が「賄賂なしでは事業が回らない体質」である場合、買収後にクリーンな経営へ転換しようとすると売上・利益が急減するリスクや、不正が露呈した際のレピュテーションリスク、日本の不正競争防止法などの海外贈賄規制への抵触リスクが生じます。
賄賂の実態は帳簿上「交際費」「雑費」等に偽装されることが多く、デューデリジェンスを実施することに加え、現地の評判調査(リファレンスチェック)や従業員インタビューなど、補完的な調査も有効です。買収後はコンプライアンス研修の実施、社内規程の整備・内部監査の実施を通じて、不正リスクの洗い出しと再発防止に取り組むことが不可欠でしょう。
2-4. 資金繰り・財務基盤の健全性
特に設立5年以内の企業や中小企業の場合、慢性的な資金繰り難に直面しているケースも多く見られます。
- 経営者が個人資金を投入して延命している
- 高利の短期借入金に頼っている
- 売上債権や在庫が膨らみ、キャッシュが枯渇している
このような企業は、資金繰り悪化を理由にM&Aによる売却を希望していることもあります。十分な調査なしに買収すると、クロージング直後に増資・追加借入が不可避となり、想定外の資金投入が必要になるおそれがあります。
そのため、負債構成(短期・長期・金利水準)、直近数期の運転資本の推移、銀行借入の契約条件・財務制限条項、将来の設備投資・運転資金需要の見込みなどを丁寧に確認し、買収後に必要となる追加資金も含めた総投資額で採算性を判断することが重要です。
2-5. 手元現金取引の多用と内部統制の弱さ
フィリピン企業の中には、現金主義的な取引慣行が残っているケースがあり、小口決済に多額の「ペソ現金」が使用されていたりするケースもあります。
このような企業では資金の流れを正確にトレースすることが難しく、裏金や私的流用、公的機関への違法な支払いの原資になっているリスクもあります。デューデリジェンスでは、売り手企業の現金出納帳と銀行口座の入出金の突合、現金残高の実査、現金取引が多い理由の妥当性などを確認することが重要です。
2-6. 現地経営ノウハウとポストM&A体制
日本企業が初めてフィリピンに進出する場合、たとえM&Aにより現地企業のオーナーになっても、現地の商習慣や労務慣行、行政機関とのコミュニケーションなど「フィリピン経営のいろは」が不足しがちです。
このギャップを埋めるために重要なのが、ポストM&Aの経営体制設計です。
- 一定期間、現経営陣・創業者に残ってもらい、経営をサポートしてもらう
- キーパーソンに対し、少数の持分継続保有や業績連動報酬(アーンアウト)を設定する
- 日本人駐在員とフィリピン人マネジメントが協働する体制を構築する
また、フィリピンは解雇規制が厳格で、一方的なレイオフが難しいため、組織再編や人員調整を前提にしたM&Aでは、法的リスク・レピュテーションリスクを十分に検討する必要があります。一方で、フィリピン人は親日的で英語力も高い人材が多く、適切なマネジメントが行われれば事業成長の大きなドライバーとなり得ます。
2-7. 譲渡対価の交渉難航(価格ギャップ)
フィリピンを含む東南アジアのM&A案件では、売り手側の価格期待が一般に高めに設定されるケースが多く、バリュエーション面で買い手・売り手のギャップが交渉を長引かせる要因となっています。日本企業がこうしたギャップを調整するためには、早期に現地FAやアドバイザーを起用し、取引スキームや交渉ルール等を工夫することが実務的な対策です。
3. おわりに:フィリピンM&Aを成功させるために
フィリピンにおけるM&Aは、成長市場へのスピーディーな参入や現地ネットワーク・人材・ライセンスの獲得、既存拠点とのシナジー創出といった観点から、非常に有効な手段です。
一方で、外資規制(ネガティブリスト・最低資本金要件)の確認、財務・税務・法務デューデリジェンスの徹底、現地経営体制や価格交渉のギャップなど、慎重な検討が欠かせません。
フィリピンでのM&Aをご検討の際は、日系企業のフィリピン進出、M&A支援を多数手がけている私たちにぜひ一度ご相談ください。